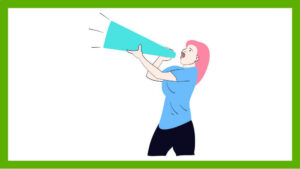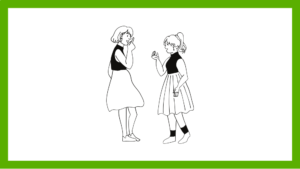「自分の子供が発達障害であることを認めないママ友にどう対応すべき?」と悩んでいる方も多いかもしれません。
お互いの子どもを想う立場だからこそ、その対応はデリケートで、慎重さが求められます。
しかし、相手がそれを受け入れず、発達障害を認めない姿勢を見せると、どう対応すれば良いのか困ってしまいますよね。
本記事では、そうした状況での対話のポイントや心がけ、関係を壊さずに相手に理解を促すためのアプローチについてご紹介します。
少しでもお役に立てる内容となれば幸いです。

私(筆者)は、2人の子供の母です。
私ができる範囲で無理なく、できるだけ楽しく子育てをしていきたいと思っています。
- 発達障害の基本的な特性と種類が理解できる。
- 親が発達障害を認めたくない理由や背景が分かる。
- ママ友に発達障害について話す際の注意点が学べる。
- 円滑な対話のために心がけるべきことが明確になる。
ママ友が発達障害を認めないのはなぜ?その背景と理由


- 発達障害とは?遺伝する?
- 発達障害による日常生活への影響
- 親が認められないその背景と理由
発達障害とは?遺伝する?
発達障害は、脳の一部が特定の機能に影響を及ぼすために、行動や対人関係、注意、学習に困難が生じる状態です。
こうした障害は個々の特性により異なり、環境要因や遺伝的要因が絡み合っていると考えられています。
| 自閉症スペクトラム障害(ASD) | コミュニケーションや社会的相互作用に困難がある。こだわり行動や反復的な行動が見られる。 |
| 注意欠陥・多動性障害(ADHD) | 注意力が散漫で集中が続かない、衝動的な行動や多動が特徴。 |
| 学習障害(LD) | 読み書きや計算が年齢相応にできないなど特定の学習面で困難がある。 |
発達障害による日常生活への影響
- 友達作りや学校での集団行動が苦手になることが多く、支援がないと不登校や社会的孤立につながる場合もあります。
- 家族も周囲の理解を得られず、生活に大きなストレスを抱えることが少なくありません。
早期に支援を受けることで、社会スキルや自己管理スキルを学ぶ機会が増え、学校生活や成人後の生活での適応力が向上します。
親が認められないその背景と理由
心理的抵抗と不安
子どもの障害を受け入れるのは精神的に大きな負担で、「親のせいではないか」と罪悪感を抱えるケースもあります。
「そんなことはない」と思うことは、自分をショックや悲しみから守るための自然な反応です。
また、 親としての自信を無くしたくないため、障害を認めたくないと感じることもあります。
社会的な偏見や誤解が影響するケース
社会的な偏見により、発達障害を「家庭環境や育て方の問題」と誤解する人も多く、偏見を恐れて公表しない親もいます。
親は子供が差別されることも恐いと思ってしまいます。
情報不足
発達障害についての知識が不足していると、親は症状を見過ごしたり、誤解したりすることがあります。
将来への不安
子供の将来に対する不安や心配が、障害を認めることを難しくすることがあります。
親は子供がどのように成長し、社会に適応していくかを心配します。
こちらのX投稿者さんも言っているように、まだまだ周囲からの厳しい目がママを苦しめていることが分かりますね。
一方で、これらXの投稿者さんたちのように、第三者としては「発達障害だな」と思っても、親が分かっていない・認められないことも、よくあるのかもしれません。
発達障害を認めないママ友との関係を保ちつつ向き合うための方法
- ママ友に発達障害について話すときのコツ
- 実際に私が同僚から話してもらったときの話
- 自分の子供が発達障害であることを認めないママ友にどう対応すべき?まとめ
ママ友に発達障害について話すときのコツ
| お互いの立場を理解するための心構え | 相手が子どもの障害を認めることに不安を抱えている可能性があるため、その心情を理解する姿勢で臨みます。 |
| 共通の関心ごとから話を切り出す方法 | たとえば、子どもの遊びや学習方法などの話題から切り出し、自然に障害について触れる流れを作り、相手の様子をうかがいます。 |
| 無理に発達障害を認めさせようとしない | 自分の意見に固執せず、相手の価値観を尊重し相手のペースで受け入れられるようにするのが効果的です。時間がかかる場合も多いです。 |
| 他のママ友や第三者を巻き込まない | 話を広げず、個別に対応します。広めないよう配慮することで、信頼関係を保てます。 |
実際に私が同僚から話してもらったときの話
実は私の子供は発達障害の診断を受けています。
その時のきっかけは、同僚でした。
同僚のお子さんも発達障害があり、数年先輩でした。
いろいろ園での出来事を聞いてもらっていたところ、違ったら違ったでいいと思うけど、少しでも気になるなら早い方がいいから、相談だけでもしてみたら?と言ってもらいました。
私はそうかもな・・と思っていたこともあり、すんなり受け入れられました。
しかも同僚のお子さんも発達障害があるので、より受け入れやすい状況でした。
私は同僚に当時も今も感謝していますし、全く嫌な気持ちにはなりませんでした。
しかし、やはり非常にデリケートな問題です。
いくら仲がいいママ友だったとしても、第三者が簡単に口出すことではないとは思います。
相談があれば相談に乗りつつ、ママ友から相談されたタイミングで「お友達でこういう子がいて、こういう所で相談したらしいよ」など、さりげなく話にだして相手の出方を見るくらいがちょうどいいかもしれません。
そして、もし相手が、「そこまでではないから~」という感じだったら、すぐその話はおしまいにする、くらいな気持ちで対応するのがいいと思います。
自分の子供が発達障害であることを認めないママ友にどう対応すべき?まとめ


- 発達障害の基本 – 脳の一部に機能的な違いがあるため、行動や対人関係に困難が生じる。
- 発達障害の主な種類 – 自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠陥・多動性障害(ADHD)、学習障害(LD)など。
- 遺伝の影響 – 発達障害は遺伝的要素が関与している可能性が高い。
- 日常生活への影響 – コミュニケーションや集団行動に困難が生じ、家庭でも負担が増えることがある。
- 早期支援の重要性 – 早期支援により社会スキルが向上し、将来的な適応力が上がる。
- 親が障害を認めない理由 – 認めることへの心理的抵抗や、偏見による影響など。
- ママ友に話す際の基本ステップ – 共通の話題から自然に話を切り出し、相手の心情を理解しつつ様子をみる。
- 円滑な対話のコツ – 知り合いの子どもの例を挙げる、専門機関の話をするなど情報共有するつもりで。
- 押し付けない姿勢が重要 – 相手の価値観を尊重し、無理に認めさせようとしない。



ママ友とママ友のお子さんのためにも早く認めてあげた方が・・と思う気持ちも十分理解できますが、難しい問題です。無理に進めず、ママ友の考えを尊重してあげてくださいね。
読んでいただきありがとうございました。
どなたかの参考になれば嬉しいです。