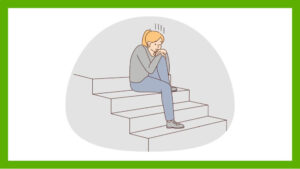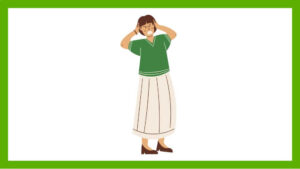学校や幼稚園・保育園生活の中で、先生が特定の保護者に対して特別な態度を取るように感じることはありませんか?
たとえば、ある保護者の意見ばかりが尊重されていたり、子どもがひいきされていると感じたりする場面。
こうした「保護者ひいき」は、表面上は些細なことに見えるかもしれませんが、子どもたちの教育環境や保護者間の関係に大きな影響を与えることがあります。
では、先生はなぜ特定の保護者をひいきするのでしょうか?
今回はその背景にある理由や、どのように対処すべきかを探っていきます。

私(筆者)は、2人の子供の母です。
私ができる範囲で無理なく、できるだけ楽しく子育てをしていきたいです。
- 幼稚園・保育園・小学校でのひいきとは何かが分かる
- 先生が特定の保護者をひいきする理由が分かる
- ひいきを避けるためのステップ・コツが理解できる
先生はなぜ特定の保護者をひいきするのか?その背景


- 教師の役割と保護者との関係性
- 「ひいき」とは?
- なぜ「保護者ひいき」が話題になるのか
- ハズレ・良くない先生の特徴は?
教師の役割と保護者との関係性
教師は子どもたちの学習と成長をサポートする役割を持っていますが、保護者との関係性も教育において重要です。
特に、家庭との連携が求められる場面では、教師と保護者が協力することが子どもたちの成績向上や心理的安定につながります。
しかし、この関係性が偏ってしまうと、特定の保護者が優遇されるように感じられる「ひいき」が生まれることがあります。
教師と保護者の関係性のポイント:
- 定期的なコミュニケーション:保護者面談や連絡帳を通じてのやり取り
- フィードバックの公平性 :すべての子どもに対して平等に評価やフィードバックを行う
- 協力体制 :保護者との信頼関係を築くことで子どもへの支援が充実する
「ひいき」とは?
「ひいき」とは、特定の人物やグループを優遇し、不公平な扱いをすることを指します。
学校現場では、特定の保護者やその子どもが、他の生徒や保護者よりも特別に扱われる場合に「保護者ひいき」が問題となります。
なぜ「保護者ひいき」が話題になるのか
保護者ひいきが話題になる背景には、学校というコミュニティにおける公平性が重要視されているためです。
すべての生徒に平等な教育機会を提供することが教育機関であるため、ひいきが疑われると他の保護者や生徒から不満が生じ、信頼を失うことになります。
また、ひいきが明らかになると、教師と保護者間のコミュニケーションにも悪影響です。
ハズレ・良くない先生の特徴は?
ひいきを行う「ハズレ」教師にはいくつかの共通点が見られます。
これらの特徴は、保護者や生徒に対する不公平な対応や、教育上の問題を引き起こす原因となります。
良くない先生の特徴:
- 特定の保護者や生徒を優遇:一部の生徒や保護者だけを優先的に褒めたり特別な待遇を与える
- 感情的な対応 :冷静さを欠き、感情で判断する
- コミュニケーション不足 :一部の保護者としか連絡を取らない
- 公平な評価ができない :特定の生徒にだけ高い成績や評価を与える
- 偏ったフィードバック :特定の家庭にのみ詳細なフィードバックを与える
先生が特定の保護者をひいきする理由と対策


- 先生が特定の保護者をひいきする理由と心理とは?
- ひいきが子どもや親に与える影響
- 先生のひいきがうざい・・と感情的にならないためのステップ
- ひいきを防ぐための親としてのコツ
- 先生はなぜ特定の保護者をひいきするのか?・まとめと私の見解
先生が特定の保護者をひいきする理由と心理とは?
先生が特定の保護者をひいきする理由にはいくつかの心理的背景があります。
多くの場合、ひいきは意図的でない場合があり、先生が特定の保護者や生徒に対して感じる親近感や依存感が関与しています。
ひいきが生じる主な理由:
- 親しみやすさ :特定の保護者とのやり取りが楽で、自然とひいきをしてしまう
- 時間の制限 :忙しさの中で、応答しやすい保護者に偏りが出る
- 依頼の頻度 :積極的に要望を出す保護者に対して対応が増える
ひいきが子どもや親に与える影響
ひいきが行われると、その影響は子どもや保護者にさまざまな形で現れます。
特に、子どもたちの間では不公平感が芽生え、自己評価や人間関係に影響を及ぼすことが考えられます。
ひいきによる影響:
- 子どもの自己肯定感の低下:公平に扱われないと感じる子どもは、自尊心が傷つく
- 友人関係の悪化 :ひいきされる子どもと他の生徒の間に溝が生まれる
- 保護者間の不信感 :保護者同士のトラブルや信頼関係が壊れる
先生のひいきがうざい・・とならないためのステップ
ひいきを避けるためには、保護者としても冷静に対応し、学校との信頼関係を保つことが大切です。
ステップ:
ひいきが疑われる場合、まずは証拠や具体的なことを整理
(学校側に伝える際は感情的にならず、事実を元にした冷静なアプローチが必要)
客観的な視点から、他の保護者とも意見交換
先生の立場や状況も理解しながら、話し合う
感情的にならず、冷静に問題点を伝える
解決しない場合は校長先生や教育委員会に相談
ひいきを防ぐための親としてのコツ
ひいきを防ぐためには、保護者自身が先生と良好な関係を築くことが重要です。
定期的なコミュニケーションや、公平性を重視した態度を心掛けることがポイントです。
コツ:
- 先生との適切な距離を保つ:親しくなりすぎず、適切な関係を維持する
- 他の保護者との情報共有 :偏った情報を防ぐために他の保護者と意見交換し客観的な意見を知る・対立を避ける
- 感謝の気持ちを伝える :良い対応があった場合には感謝を伝え、ポジティブな関係を築く
- 定期的な連絡 :面談や連絡帳を活用して、負担にならない程度に定期的に先生とやり取りする
- 感情を押さえる :感情的にならず、冷静に要望や問題を伝える
先生はなぜ特定の保護者をひいきするのか?・まとめと私の見解


まとめ
- 子どもの教育環境を守るため、親も積極的に対話し、冷静に対応する姿勢が大切。
- 教師と保護者の関係性は、子どもたちの教育環境に大きな影響を与え、公平な対応が求められる。
- 先生が特定の保護者をひいきする背景には、親しみやすさや頻繁なコミュニケーションが影響していることが多い。
- ひいきが与える影響として、子どもの自己肯定感の低下や友人関係の悪化が挙げられる。
- ひいきを防ぐためには、冷静に事実を確認し、学校側と建設的な対話を行うことが重要。
- 親としてのコツは、先生との適切な距離を保ち、他の保護者と情報を共有すること。
- 先生に対して問題を指摘する際は、冷静に事実に基づいた話し合いを行い、感情的な対応を避ける。
私の個人的な見解
私自身コミュニケーションが苦手なこともあり、保育園でも小学校でも先生との距離感は悩みました。
でも、幸いなことにあからさまな「ひいき」をするような先生はいませんでした。
ただ、私のコミュニケーションの苦手さがあるからか、先生からもフレンドリーな対応してもらえず、他の保護者との差を感じることはありました。
保育園・幼稚園・学校は公平性を求められる場所ではありますが、完璧には難しいです。
保護者としてもあの先生はいいけど、この先生はちょっと・・というのもあると思います。
先生も保護者も人間ですから、好みもありますし、気持ちもあります。
大事なことは、先生に感謝の気持ちを忘れずに、笑顔であいさつや必要な情報共有をする。
さらに、保護者として提出物や行事についてしっかりと把握して行動ができていれば、問題ないのかなと思います。
無理せずできることをやり、子供の社会生活を応援していきましょう!



読んでいただきありがとうございました。
どなたかの参考になれば嬉しいです。